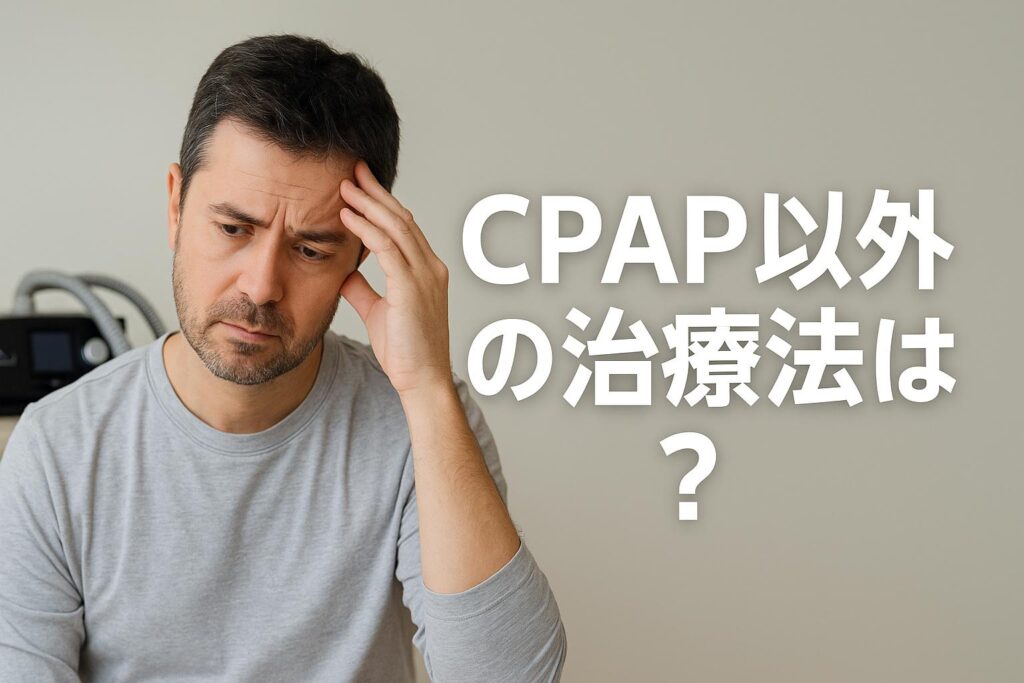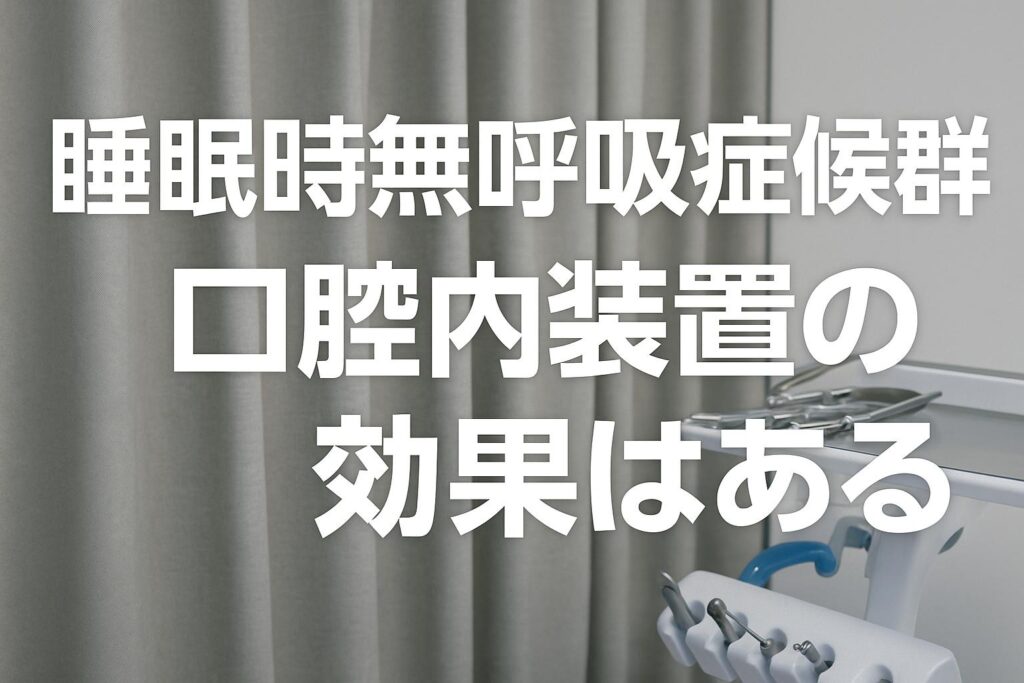
口腔内装置とは?
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療と聞くと、多くの人が思い浮かべるのはCPAP(シーパップ)療法かもしれません。しかし、すべての人がCPAPを快適に使えるとは限らず、「マスクの装着がつらい」「機械音が気になる」といった理由から、別の治療法を探している人も多くいます。
そんな中で注目されているのが「口腔内装置(マウスピース)」です。これは、就寝中に口の中に装着することで気道の閉塞を防ぎ、無呼吸の発生を抑える装置です。特に軽度〜中等度の閉塞型睡眠時無呼吸症候群(OSA)に対しては、効果的な選択肢の一つとされています。
この記事では、口腔内装置の仕組みや種類、メリット・デメリット、費用や保険適用の条件まで詳しく解説していきます。
睡眠時無呼吸症候群の仕組みと口腔内装置の役割
睡眠時無呼吸症候群の多くは「閉塞型」と呼ばれるタイプで、睡眠中にのどの奥の気道が塞がれることで呼吸が止まります。特に仰向けで寝ていると、舌根が喉の奥に落ち込むことで気道がふさがれやすくなります。
口腔内装置はこの問題を物理的に解決するために設計されています。装着することで、舌や下あごの位置を前方に固定し、気道のスペースを確保。これにより、空気の流れをスムーズに保ち、いびきや無呼吸を防ぐ効果が期待されます。
口腔内装置の種類と仕組み
口腔内装置にはいくつかのタイプがあり、それぞれ仕組みや適応が異なります。ここでは代表的な2種類をご紹介します。
下顎前方移動型装置とは?
もっとも一般的に使われているのが「下顎前方移動型装置」です。この装置は上下の歯にマウスピースを装着し、下あごを少し前に突き出した状態で固定する仕組みです。これにより舌が喉の奥に落ちるのを防ぎ、気道の閉塞を防ぎます。
このタイプの装置は、歯科で一人ひとりの顎の形や噛み合わせに合わせて製作され、装着時の違和感も少なくなるように設計されています。
【特徴】
-
効果が高く、広く使用されている
-
個別に調整可能で快適性が高い
-
慣れれば毎晩の装着もスムーズ
【注意点】
-
顎関節に負担がかかる場合がある
-
長期間の使用で歯並びに影響が出ることもある
舌保持型装置とは?
もう一つのタイプが「舌保持型装置(TRD)」です。これは下あごの位置を動かすのではなく、舌自体を前方に引っ張って固定することで気道を広げる仕組みです。
主に義歯の人や、顎関節症などで前方移動型の装置が使えない人に対して用いられます。ただし、装着時の違和感が大きいため、使用を継続するのが難しいと感じる人もいます。
【特徴】
-
顎に負担をかけずに使用できる
-
一部の症例に限定的に適応される
【注意点】
-
舌に違和感を覚えやすい
-
使用者の満足度は低め
メリット・デメリットを比較
口腔内装置は手軽に導入できる反面、万能な治療法ではありません。以下に代表的なメリットとデメリットをまとめました。
メリット
-
CPAPより装着感が軽く、違和感が少ない
マスクやホースを必要とせず、装置も小型で寝返りなども妨げにくい。 -
持ち運びが容易で旅行や出張でも使用しやすい
CPAP機器と比べてコンパクトなので携帯性に優れる。 -
軽度〜中等度のSASに対しては高い効果が期待できる
AHI(無呼吸低呼吸指数)が改善されたとの報告も多数ある。
デメリット
-
重度の無呼吸症候群には効果が限定的
CPAP療法のような気道への強制的な空気圧送ができないため、重症例には不向き。 -
長期間使用で顎関節や歯列に影響を与えることがある
あごの関節に負担がかかったり、かみ合わせが変わるケースも。 -
装着中に唾液の量が増えたり、口が乾くなどの副作用
個人差はあるが、慣れるまで不快感を覚える人もいる。
保険適用と費用の目安
日本では、睡眠時無呼吸症候群と診断されたうえで医師が必要と判断した場合、口腔内装置の作製には健康保険が適用されます。保険適用の条件や費用の目安は以下の通りです。
-
保険適用の条件
・閉塞型SASと診断されていること
・重症度が軽度〜中等度であること
・CPAPが不適または使用困難であること
・医師の紹介で対応する歯科を受診すること -
費用の目安(3割負担の場合)
約15,000円〜20,000円前後
※自由診療の場合は3〜7万円程度かかるケースもあります
作製後は、定期的なメンテナンスや調整が必要です。保険が適用されるのは初回のみで、以降の調整料や再製作は自己負担になる場合もあるため注意が必要です。
使用時の注意点と効果的な活用法
口腔内装置は医師と歯科医師の指導のもとで正しく使うことが前提です。以下のような点に注意すると、より効果的に活用できます。
-
定期的に装着状態をチェックすること
装置のゆがみや歯への圧力が強すぎる場合、かえって口腔トラブルの原因になります。 -
就寝前の飲酒や過食は避けること
筋肉が弛緩しやすくなり、装置の効果が十分に発揮されないことがあります。 -
乾燥対策として口腔内の保湿を意識する
口の中が乾きやすい人は、寝る前のうがいや保湿ジェルの使用もおすすめです。 -
使用初期は違和感があることを理解しておく
初めは眠れないと感じるかもしれませんが、1〜2週間程度で慣れるケースが多いです。
こんな人におすすめ!口腔内装置チェックリスト
以下に該当する方は、口腔内装置の使用を検討する価値があります。
| 該当項目 | チェック |
|---|---|
| CPAPがどうしても合わない | □ |
| いびきや軽度の無呼吸をパートナーに指摘された | □ |
| 出張・旅行が多くCPAPの持ち運びが負担 | □ |
| 歯が健康で、顎関節症などがない | □ |
| 保険適用の条件に当てはまっている | □ |
| 舌が喉に落ちやすいと診断された | □ |
3つ以上当てはまる方は、一度専門医に相談してみるとよいでしょう。
まとめ:自分に合った治療法のひとつとして検討を
睡眠時無呼吸症候群は、放置すると心筋梗塞や脳卒中などの重大なリスクを招く恐れがあります。CPAP療法が難しいと感じる方にとって、口腔内装置は現実的かつ有効な代替手段となり得ます。
特に軽度から中等度の症状であれば、口腔内装置だけで大きな改善が見込めることもあります。ただし、使用には歯や顎の健康状態、適切な診断と装置の管理が必要不可欠です。
自身のライフスタイルや体の状態に合わせて、最適な治療法を選ぶことが、快適な睡眠と健康な日常生活を取り戻す第一歩となります。
参考・引用URL
・日本睡眠学会「睡眠時無呼吸症候群の治療と口腔内装置」
https://jssr.jp/data/pdf/sas_dental.pdf
・厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠時無呼吸症候群」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-004.html
・日本歯科医学会連合「睡眠時無呼吸とマウスピース治療」
https://www.jads.jp/public/sleepapnea/