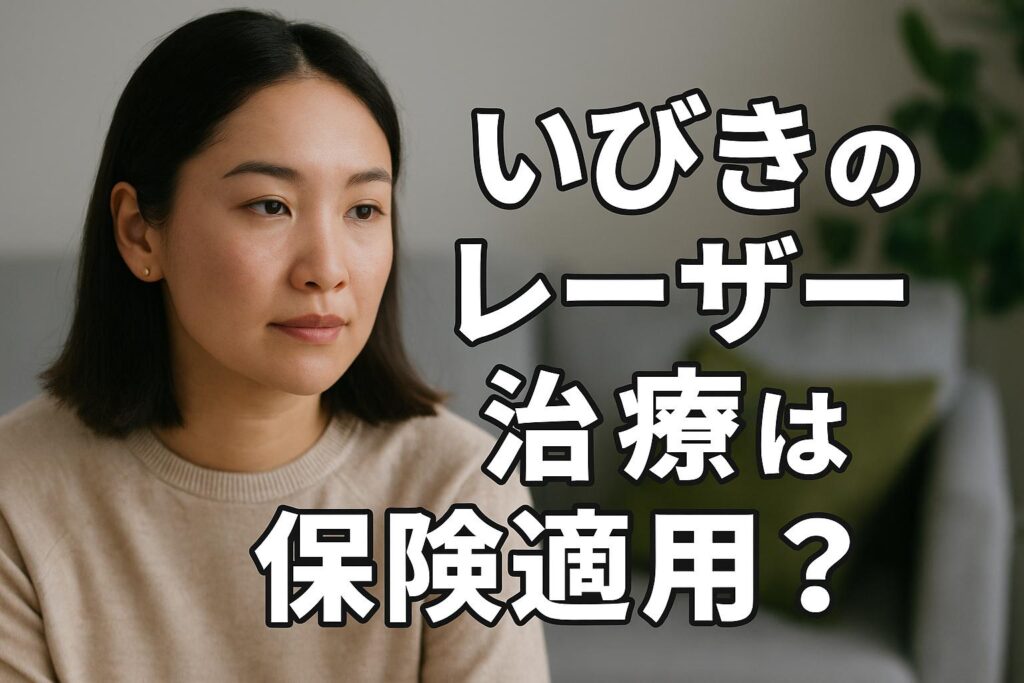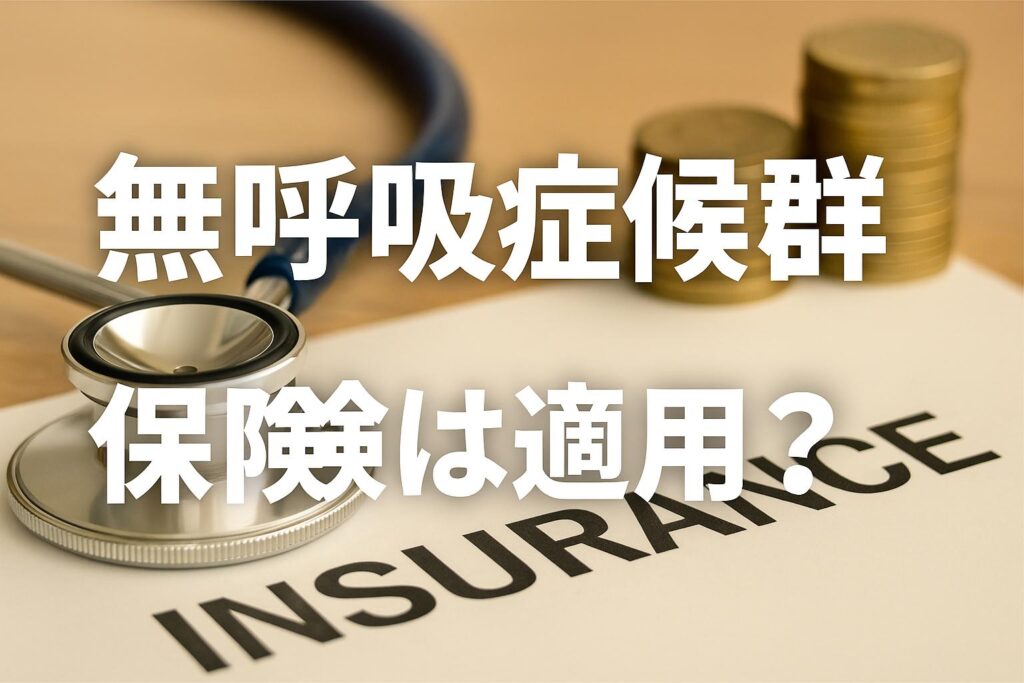なぜ「無呼吸時間」と「回数」が重要なのか
「睡眠中に呼吸が止まっている」と言われたことはありませんか?その背後には、睡眠時無呼吸症候群(SAS)という疾患が潜んでいるかもしれません。この病気の診断や重症度を評価する上で非常に重要なのが、「無呼吸の時間」と「回数」です。
単に「いびきをかいている」だけではなく、1回の無呼吸がどれくらいの時間続き、それが1時間あたり何回起こっているのかを把握することが、治療方針を決定する上で不可欠です。
本記事では、SASの診断基準において中心となるAHI(無呼吸低呼吸指数)の意味から、実際の無呼吸時間と回数の平均、健康リスクとの関係、そしてどのようにそれらを調べるかまでを詳しく解説していきます。
睡眠時無呼吸症候群の定義と診断基準
無呼吸と低呼吸の違い
睡眠時無呼吸症候群の症状は大きく2つに分けられます。
-
無呼吸(Apnea):10秒以上、呼吸が完全に止まっている状態
-
低呼吸(Hypopnea):呼吸はしているが、通常の50%以上の換気量が減少し、かつ酸素飽和度(SpO₂)が3~4%以上低下している状態
これらが睡眠中に何度も繰り返されることで、脳や身体への酸素供給が阻害され、日中の眠気や集中力の低下、さらには高血圧・心疾患などの深刻な合併症につながることがあります。
AHI(無呼吸低呼吸指数)とは
AHI(Apnea Hypopnea Index)とは、1時間あたりに起こる無呼吸+低呼吸の回数を示す指標です。この値によって睡眠時無呼吸症候群の重症度が分類されます。
| AHIの値 | 重症度 |
|---|---|
| 5未満 | 正常〜軽度 |
| 5〜15未満 | 軽度 |
| 15〜30未満 | 中等度 |
| 30以上 | 重度 |
たとえば、AHIが「30」という人は、1時間に30回以上も呼吸が止まったり浅くなったりしているということです。8時間睡眠をとっていれば、合計240回以上も呼吸障害が起きていることになります。
無呼吸1回の時間と1時間あたりの回数の目安
実際の無呼吸時間はどのくらい?
一般的に、1回の無呼吸エピソードは10〜30秒程度が多いとされています。しかし、重度のSAS患者の場合には1回の無呼吸が60秒以上続くこともあります。まれに、90秒以上に及ぶケースもあり、その間に体内の酸素が急激に低下してしまいます。
以下は、無呼吸の持続時間とその影響をまとめた表です。
| 無呼吸時間 | 身体への影響 |
|---|---|
| 10〜20秒 | 比較的軽度、SpO₂の低下は限定的 |
| 20〜40秒 | 酸素飽和度が大きく下がり始める |
| 40〜60秒 | 心拍数増加、脳が覚醒状態になりやすい |
| 60秒以上 | 臓器への酸素供給が深刻に阻害されるリスクあり |
このように、1回の無呼吸が長ければ長いほど、身体へのダメージは大きくなります。1回あたりの時間だけでなく、「そのような無呼吸が何回繰り返されているか」も見逃せないポイントです。
回数が多いと何が起こる?
回数が増えれば、それだけ睡眠の質が損なわれ、健康への影響も深刻になります。たとえば、1時間あたりに40回の無呼吸が起これば、1分半ごとに呼吸が止まるということになります。
以下のような症状・疾患との関連性が強く報告されています。
-
慢性的な日中の眠気
-
集中力や記憶力の低下
-
うつ症状や情緒不安定
-
高血圧、心筋梗塞、脳卒中
-
2型糖尿病やメタボリックシンドローム
無呼吸の回数が多いほど、これらのリスクが指数関数的に高まるという研究もあります。
無呼吸時間・回数を測る方法
自宅でできる簡易検査とは
SASが疑われる場合、まずは自宅での簡易検査からスタートすることが多いです。これは「簡易型終夜睡眠呼吸モニター」などと呼ばれる検査で、指先や鼻のセンサーを装着し、以下のような項目を測定します。
-
酸素飽和度(SpO₂)
-
呼吸の回数と中断
-
心拍数
-
いびき音や体動
数時間の睡眠データを取得するだけで、AHIの推定値が算出され、簡単な診断に役立ちます。保険適用される場合もあり、費用は数千円〜1万円程度が目安です。
PSG(終夜睡眠ポリグラフ検査)とは
より精密な診断が必要な場合は、**病院や専門施設で行う「終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)」**が用いられます。これは睡眠中の脳波、眼球運動、筋電図、心電図、呼吸の流れ、酸素濃度などを同時に測定する検査で、SASの正確な重症度や原因の特定に役立ちます。
-
検査時間:1泊(夕方入院〜翌朝退院)
-
費用:保険適用時で1〜2万円前後(3割負担)
-
判定までに数日かかるが、診断精度は高い
PSGは特に、無呼吸のタイプ(閉塞型・中枢型・混合型)を識別したい場合や、治療方針を決定する上で重要な検査です。
無呼吸時間が長い・回数が多い人が注意すべきこと
以下のような特徴がある人は、無呼吸の時間が長く、回数も多くなりやすいため、特に注意が必要です。
-
肥満体型(BMI25以上)
-
首回りが太い(男性40cm以上、女性35cm以上)
-
アルコールを習慣的に飲む(特に就寝前)
-
鼻づまりやアレルギー性鼻炎を抱えている
-
顎が小さい、または後退している
-
高血圧や糖尿病などの基礎疾患がある
上記に当てはまる方は、早期に検査を受けて無呼吸の状態を確認することが推奨されます。
よくある誤解と注意点
「いびきがないから無呼吸じゃない」は誤解
いびきがある人にSASが多いのは確かですが、いびきがなくても呼吸が止まっている人は存在します。特に無呼吸が長い場合、いびきの音が出る間もなく呼吸が止まるため、家族に気づかれにくいこともあります。
「昼間に眠くないから問題ない」も危険
日中の眠気を自覚していなくても、脳や心臓には確実にダメージが蓄積していきます。無呼吸の影響は年単位で現れるため、症状がなくても検査は受けるべきです。
まとめ:自分の無呼吸の状態を正しく知ろう
睡眠時無呼吸症候群は、「無呼吸の時間」と「1時間あたりの回数」を知ることが診断の出発点です。たとえ1回の無呼吸が短くても、それが何十回も繰り返されれば、脳と体に与える影響は非常に大きなものになります。
AHIという指標を通じて重症度を把握し、必要に応じてCPAP療法や口腔内装置、生活習慣の改善など適切な治療を受けることが重要です。
「ただのいびき」で済ませず、自分の睡眠を見直すことが、健康的な人生を送る第一歩になります。
参考・引用URL
・厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠時無呼吸症候群」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-004.html
・日本睡眠学会「睡眠時無呼吸症候群の診断と治療」
https://jssr.jp/data/pdf/sas_guideline_2020.pdf
・全国SASネット「AHIと重症度分類」
https://www.sas-japan.org/