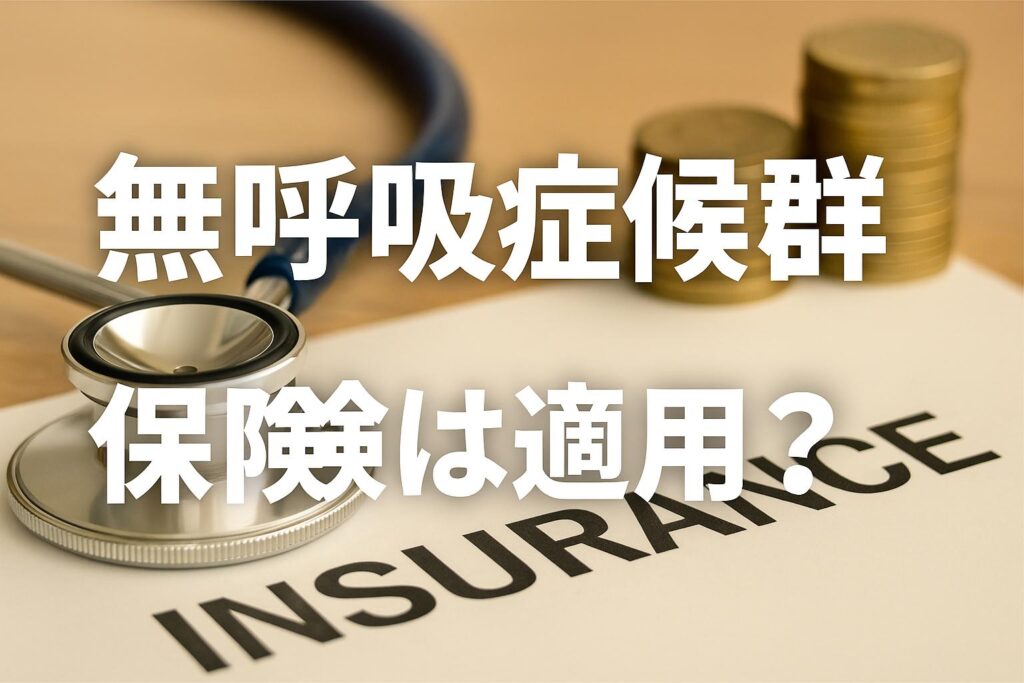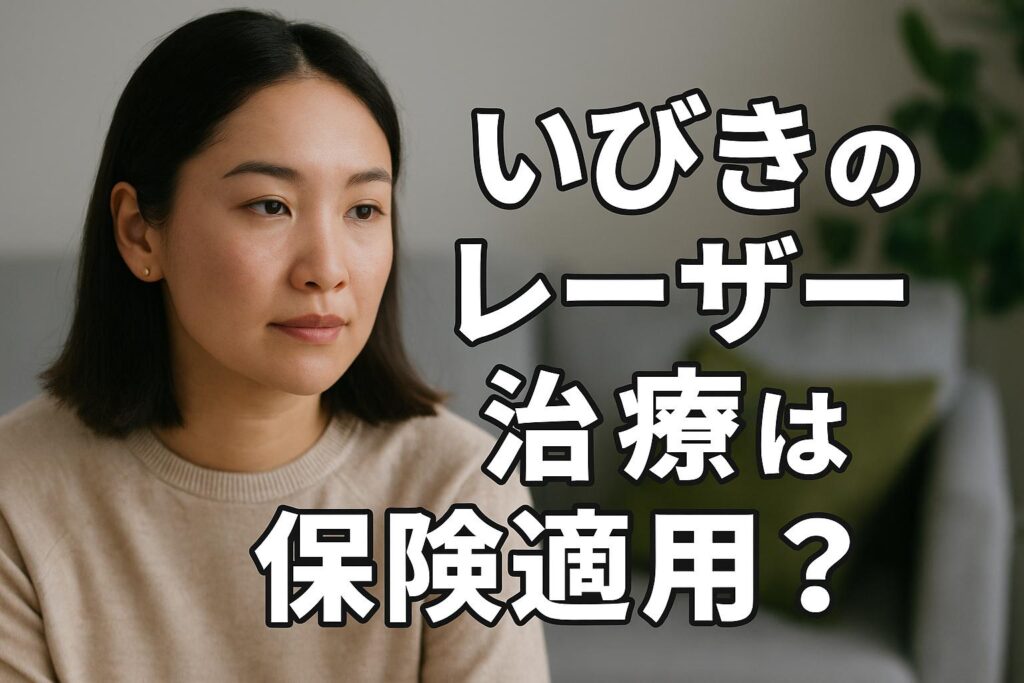いびきがうるさい=病気の可能性?
寝ている間のいびき。本人は無自覚でも、家族やパートナーにとっては「うるさい」「眠れない」と深刻な問題になりがちです。中には「壁越しでも聞こえるほど大きないびき」をかく人もいますが、ただの音の問題として放置していませんか?
実はいびきの大きさや頻度には、体の中で起きている異変が反映されていることがあります。特にうるさいいびきは、何らかの病気の兆候である可能性があり、見逃すことで将来の健康リスクを高めてしまうことにもつながります。
この記事では、いびきをかいている人がかかっている可能性のある病気や、いびきが原因で将来的に発症するかもしれない病気について、詳しく解説していきます。
いびきがうるさい人がかかっている可能性のある病気
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
うるさいいびきの代表的な原因のひとつが、**睡眠時無呼吸症候群(SAS)**です。これは睡眠中に何度も呼吸が止まる病気で、気道が塞がれることで空気の流れが遮断され、その際に「ガッ」「ブフッ」といったいびきや呼吸の再開時の大きな音が生じます。
とくに以下のような特徴がある人は要注意です。
-
一晩中いびきをかいている
-
息が止まっていると家族に指摘される
-
起床時に頭痛やだるさがある
-
日中に強い眠気がある
SASは重度になると、高血圧・心疾患・脳卒中などのリスクを高めるため、早期の発見と治療が重要です。
肥満症
肥満は、いびきと密接に関係する病態です。特に首まわりに脂肪が蓄積されていると、気道が圧迫されて狭くなり、呼吸時に強い振動音(=いびき)が発生しやすくなります。
肥満傾向の人でいびきがひどい場合、単に体重だけでなく、肥満症としての病的な影響が出ている可能性があります。生活習慣病のリスクを含めて、いびきはひとつの健康指標ととらえることが大切です。
アレルギー性鼻炎・鼻中隔湾曲症などの鼻の病気
鼻づまりが慢性化している人は、口呼吸になりやすく、結果としていびきをかきやすくなります。鼻の通りが悪いと空気がのどの奥を通過する際に乱流が起こり、これが振動音(いびき)につながります。
鼻が原因のいびきは以下のような病気に関連することがあります。
-
アレルギー性鼻炎
-
慢性副鼻腔炎(蓄膿症)
-
鼻中隔湾曲症
-
鼻ポリープ
これらの疾患は耳鼻科での診断・治療によって改善できることが多いため、鼻づまりといびきが両立している人は早めの受診をおすすめします。
扁桃肥大・アデノイド肥大(特に子ども)
子どもでいびきがうるさい場合、扁桃腺やアデノイド(咽頭扁桃)の肥大が原因であることが少なくありません。これらが気道をふさぎやすくし、呼吸音を大きくするだけでなく、睡眠の質にも悪影響を与えます。
子どもが以下のような症状を示していたら、耳鼻咽喉科への相談を検討しましょう。
-
就寝中に何度も呼吸が止まる
-
寝汗がひどい
-
口呼吸が常態化している
-
集中力が続かない、朝起きづらい
放置すると発育や学習に悪影響を与える可能性があるため、軽視できません。
いびきをかくことで生じる病気・リスク
うるさいいびきをそのまま放置していると、単なる睡眠の問題にとどまらず、全身の健康に深刻な影響を及ぼすことがあります。特に「いびき+無呼吸」が繰り返されている場合、以下のような病気の発症リスクが高まります。
高血圧・心臓病・脳卒中
睡眠時無呼吸症候群をはじめ、慢性的ないびきによって体が繰り返し「酸欠状態」に陥ると、自律神経が常に緊張状態になります。これにより血圧が上がりやすくなり、高血圧を引き起こす原因となります。
さらに、心臓への負担が増えることで、
-
心筋梗塞
-
不整脈
-
狭心症
といった心血管系の病気にもつながる恐れがあります。また、脳への酸素供給が不安定になることで、脳卒中や**一過性脳虚血発作(TIA)**のリスクも上昇します。
糖尿病・メタボリックシンドローム
いびきと無呼吸の繰り返しは、インスリン抵抗性の悪化とも関係があるとされています。つまり、体が血糖をうまく処理できなくなり、2型糖尿病の発症リスクが高くなるのです。
特に肥満とセットでいびきをかいている人は、「メタボリックシンドローム」の可能性も視野に入れ、医療機関での検査を受けることが推奨されます。
うつ病・認知症との関係
睡眠の質が低下すると、脳の回復機能が十分に働かなくなり、情緒の不安定化や抑うつ症状を引き起こすことがあります。いびきによって睡眠が断片化されると、以下のような精神的症状が現れやすくなります。
-
日中の強い眠気
-
集中力や判断力の低下
-
イライラや不安感
-
抑うつ傾向や無気力感
また、近年では睡眠障害とアルツハイマー型認知症の関連性も注目されており、深い睡眠がとれない状態が長期間続くことで、脳の老廃物排出がうまく機能せず、認知機能の低下につながる可能性があるとされています。
自分のいびきは病気?セルフチェックリスト
いびきが単なる癖なのか、それとも病的なレベルなのか、自分で判断するのは難しいものです。以下の項目に複数該当する場合、医療機関での相談を検討しましょう。
いびきセルフチェックリスト
| チェック項目 | YES / NO |
|---|---|
| 家族やパートナーにいびきを指摘される | ☐ ☐ |
| 「いびきがうるさすぎる」と言われたことがある | ☐ ☐ |
| 寝ている間に呼吸が止まっていると指摘された | ☐ ☐ |
| 起床時に頭痛・だるさ・喉の痛みがある | ☐ ☐ |
| 日中に強い眠気を感じる | ☐ ☐ |
| 肥満ぎみで首が太いと感じる | ☐ ☐ |
| 鼻づまりやアレルギー性鼻炎がある | ☐ ☐ |
| 睡眠薬やお酒を常用している | ☐ ☐ |
3つ以上当てはまる場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いため、専門医の診断を受けることをおすすめします。
いびきがひどいときに受けるべき検査と対策法
うるさいいびきを自覚していたり、家族やパートナーから指摘されている場合は、放置せずに専門の医療機関で検査を受けることが重要です。
睡眠時無呼吸症候群の検査方法
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断には、主に以下の2つの検査があります。
簡易検査(自宅で実施)
携帯型の測定器を使用し、自宅で睡眠中の呼吸の状態や酸素濃度、心拍数などを測定します。比較的手軽に受けられ、1泊で結果が出ます。
精密検査(PSG:ポリソムノグラフィー)
病院に一泊して、より詳細に脳波、眼球運動、筋電図、呼吸、心電図などを測定する検査です。より正確にSASの重症度を評価するために行われます。
検査によって1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数(AHI値)を算出し、以下のように分類されます。
| AHIの値 | 重症度分類 |
|---|---|
| 5~15未満 | 軽症 |
| 15~30未満 | 中等症 |
| 30以上 | 重症 |
いびきに対する治療法と保険適用
検査の結果に応じて、さまざまな治療法が選択されます。以下に代表的な治療法と特徴を紹介します。
CPAP療法(シーパップ)
中等症〜重症のSASに対して最も効果的とされる治療法です。就寝中に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道の閉塞を防ぎます。健康保険が適用され、毎月の自己負担は3割で約4,000〜5,000円程度です。
口腔内装置(マウスピース)
軽症〜中等症に有効で、下あごを前方に固定することで気道を広げます。歯科医で作製され、こちらも保険適用の対象となる場合があります。
外科手術・レーザー治療
扁桃やアデノイドの肥大が原因の場合、摘出手術が行われることがあります。また、自由診療で軟口蓋を縮小させるレーザー治療もありますが、保険は適用されません。
生活習慣の見直し
医療的な治療に加え、以下の生活習慣の改善も非常に重要です。
-
減量(特に首まわりの脂肪を落とす)
-
飲酒・喫煙を控える
-
鼻づまりの改善
-
寝る姿勢の工夫(横向きで寝るなど)
-
毎日の口腔筋トレーニング
まとめ:うるさいいびきを放置しないために
「いびきがうるさい」と言われてショックを受けるかもしれませんが、それは体が発している重要なサインかもしれません。とくに睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、単なる音の問題ではなく、命に関わる病気につながるリスクがあります。
いびきの原因は人それぞれですが、自己判断せずに一度しっかりと検査を受けてみることで、適切な対策が見えてきます。生活習慣の見直しから医療的な治療まで、自分に合った方法で健康的な睡眠を取り戻しましょう。
参考・引用URL
・厚生労働省 e-ヘルスネット「いびき」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-006.html
(厚生労働省)
・日本睡眠学会「睡眠時無呼吸症候群 診断と治療の手引き」
https://jssr.jp/data/pdf/sas_guideline_2020.pdf
(日本睡眠学会)
・いびき対策ナビ「いびきと病気の関係性について」
https://www.snore-navi.jp/snore/sick/
(いびき対策ナビ)