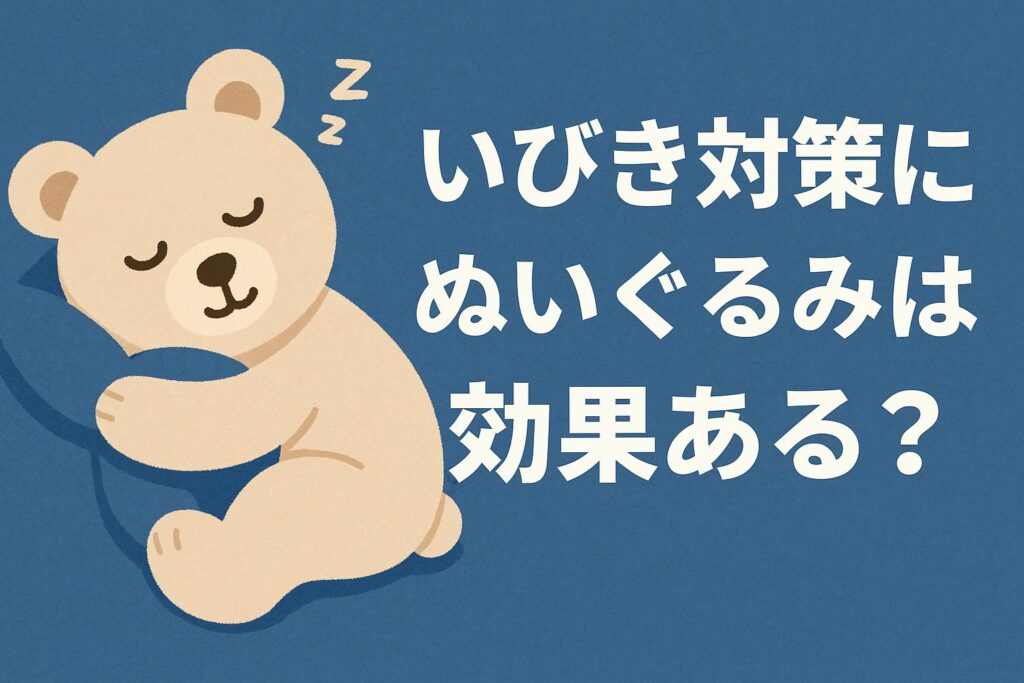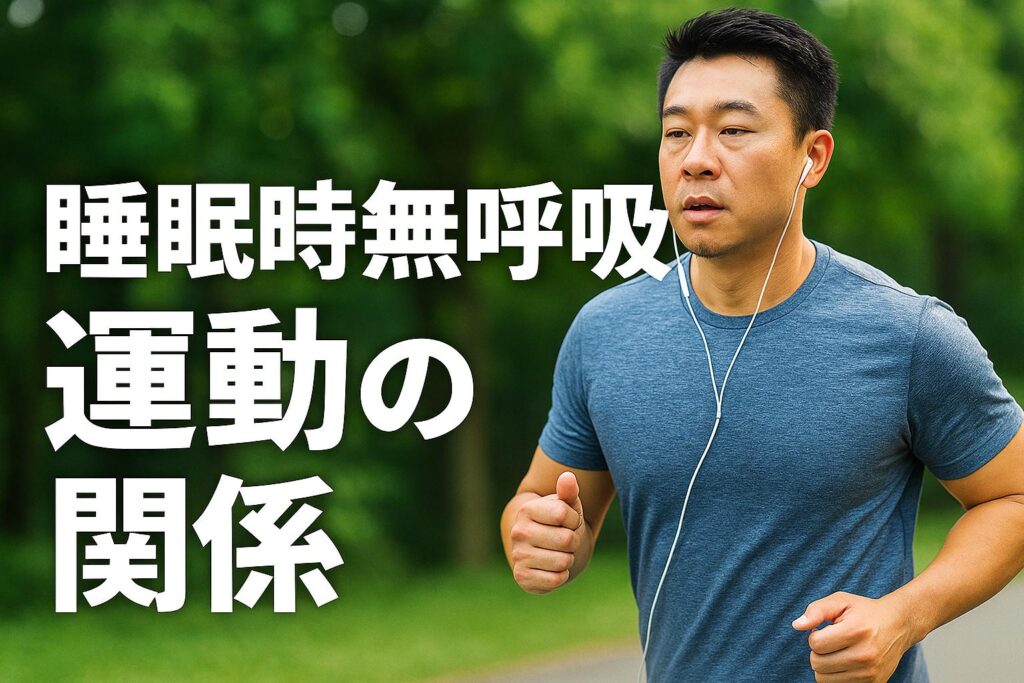
運動は睡眠時無呼吸症候群に効くのか?
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、眠っている間に呼吸が何度も止まる病気で、日中の強い眠気や集中力の低下、高血圧、心疾患などのリスクを高める深刻な症状です。その治療にはCPAP(シーパップ)療法が一般的ですが、近年、薬や機器に頼らずに改善を目指す「運動療法」に注目が集まっています。
特に軽度から中等度の睡眠時無呼吸症候群の人にとって、運動は症状の改善に大きく寄与する可能性があります。この記事では、ジョギングなどの有酸素運動とともに、あまり知られていない“舌や口まわりを鍛える運動”についても詳しく解説していきます。
睡眠時無呼吸症候群の原因と運動の役割
SASの主な原因は、睡眠中に気道が塞がれることで呼吸が止まる「閉塞型睡眠時無呼吸(OSA)」です。特に次のような要因が気道の狭窄を引き起こしやすくします。
-
肥満による首周りの脂肪蓄積
-
筋肉の緩み(加齢や飲酒の影響)
-
顎や舌の位置異常
-
鼻づまりやアレルギーによる気道の閉塞
ここで重要になるのが「運動」の役割です。運動は体重を減らすだけでなく、呼吸に関わる筋肉を鍛え、気道の閉塞を防ぐ効果もあるとされています。さらに、運動習慣を持つことで睡眠の質そのものが向上し、SASの症状改善にもつながります。
有酸素運動(ジョギング・ウォーキングなど)の効果
運動による体重減少と気道の確保
肥満は睡眠時無呼吸症候群の最大のリスク因子の一つです。首や舌の周囲に脂肪がつくと気道が圧迫され、呼吸がしにくくなります。有酸素運動は体脂肪の燃焼に効果的で、継続的に行うことで体重減少を促し、気道の確保に大きく貢献します。
特に、週に3〜5回のペースで30分〜1時間程度のウォーキングやジョギングを行うことが推奨されています。急激に体重を減らす必要はなく、無理のない範囲で長く続けることが大切です。
運動が睡眠の質にもたらす変化
運動は、SASに直接作用するだけでなく、睡眠そのものの質を高める効果もあります。以下は、運動がもたらす睡眠改善の代表例です。
-
深いノンレム睡眠の割合が増える
-
寝つきが良くなる
-
中途覚醒が減る
-
ストレスや不安が軽減される
これらの効果により、CPAPやマウスピースといった治療法と併用することで、SASの全体的な改善が期待できます。
舌やのど周りの筋肉を鍛える運動
ジョギングなどの全身運動に加えて、舌や口まわりの筋肉をピンポイントで鍛える「口腔筋トレーニング」も注目されています。この方法は器具を使わず自宅でできるため、特に軽度のSASやCPAPが苦手な方に推奨されています。
口腔筋トレーニングとは?
口腔筋トレーニングとは、舌、軟口蓋、咽頭周辺の筋肉を強化することで、睡眠中に気道がふさがるのを防ぐ運動です。ブラジルやドイツではこの分野の研究が進んでおり、「オーラル・エクササイズ」とも呼ばれます。
研究によると、口腔筋トレを3ヶ月以上継続した患者は、無呼吸の回数(AHI)やいびきの音量が有意に減少したという報告もあります。
具体的な舌のトレーニング方法(例付き)
以下に代表的な口腔筋トレーニングを紹介します。1日10〜15分程度を目安に、無理のない範囲で毎日続けましょう。
-
【舌の前方押し出し】
舌をできるだけ前に突き出し、5秒間キープ。これを10回繰り返します。 -
【舌で上あごを押す】
舌を上あご(口蓋)に押しつけて5秒間キープ。これも10回繰り返します。 -
【口を大きく開ける】
口を「ア」と大きく開き、のどの奥の筋肉を意識しながら5秒間保つ。10回繰り返す。 -
【発音トレーニング】
「ア・エ・イ・ウ・エ・オ・ア・オ」と大きな声でゆっくり発音する。これにより舌と口まわりの筋肉が刺激されます。
これらの運動は、特別な器具も場所も必要なく、日常生活の中に取り入れやすい点が魅力です。
運動療法を続けるためのチェックリスト
運動療法は継続することで初めて効果を発揮します。続けるためには「続けやすい習慣」にすることが大切です。以下のチェックリストを参考に、日常生活の中に自然に取り入れてみましょう。
| 継続のコツ | 実践ポイント |
|---|---|
| 毎日決まった時間に行う | 朝の散歩、昼休みのウォーキングなどルーティン化する |
| 目標を小さく設定する | まずは週2回、10分からスタートでもOK |
| 楽しみながら運動する | 音楽を聴きながら歩く、景色を楽しむ、家族と一緒に取り組むなど |
| 記録をつける | スマートウォッチやアプリで歩数や距離、体重の変化を記録する |
| 口腔筋トレは「ながら」で実施 | 歯磨き後やテレビ視聴中など、習慣に紐づけることで忘れにくくなる |
無理をせず、少しずつ習慣化していくことで、運動がストレスなく続けられるようになります。
注意点と運動療法の効果的な進め方
医師の診断を受けた上で取り組む
睡眠時無呼吸症候群は重症度によって治療方針が異なります。自己判断で運動だけに頼るのは危険です。特に中等度〜重度の場合はCPAPや医師の管理下での治療が必要なこともあります。運動療法を取り入れる際は、必ず専門医と相談し、自身の状態に合った方法で取り組むようにしましょう。
やりすぎや不規則な時間の運動に注意
過度な運動や、就寝直前の激しい運動はかえって交感神経を活性化させ、眠りを浅くする原因になります。運動は夕食前〜就寝の2〜3時間前までに行うのが理想です。また、無理に長時間続けるよりも、短時間でも毎日継続することが効果的です。
食事と合わせた生活習慣の改善が重要
運動だけでなく、食事内容や生活リズムもSAS改善には欠かせません。特に夕食の量を減らす、就寝前の飲酒を控える、夜更かしを避けるなど、基本的な生活習慣の見直しが相乗効果を生みます。
まとめ:継続できる運動で無呼吸を改善しよう
睡眠時無呼吸症候群の改善において、運動は非常に有効な手段のひとつです。ジョギングやウォーキングなどの有酸素運動は、体重減少を通じて気道の圧迫を防ぎ、根本的な改善につながる可能性があります。
また、舌やのど周りを鍛える口腔筋トレーニングは、筋肉の緩みを防ぎ、呼吸しやすい状態を保つうえで役立ちます。どちらも道具を使わずに始められるため、日常生活の中に取り入れやすく、継続しやすいのが特徴です。
大切なのは、「完璧を目指す」ことではなく、「続けることを目指す」ことです。無理のない範囲で、生活スタイルに合わせた運動を取り入れ、快適な睡眠と健康を取り戻していきましょう。
参考・引用URL
・厚生労働省「睡眠障害対処 12の指針」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-004.html
・独立行政法人国立健康・栄養研究所「肥満と睡眠時無呼吸」
https://www.nibiohn.go.jp/eiken/
・アメリカ睡眠医学会(AASM)“Behavioral Interventions for OSA”
https://aasm.org/resources/factsheets/sleepapnea.pdf(英語)
・京都大学医学部「睡眠時無呼吸と運動療法に関する研究報告」
https://www.med.kyoto-u.ac.jp/(※概要ページ)